――CR?インレー?クラウン? 自分の“修復基準”を持とう
「カリエスは取りきれた。さて、どう修復するか——。」
削る前には「ここはCRで…」「このケースはクラウンだな」と治療方針を立てていたはずなのに、いざ窩洞を目の前にすると悩む——そんな経験はありませんか?
若手歯科医師にとって、“削った後”の判断は予想以上にプレッシャーが大きいものです。
【修復の選択は“削る前”から始まっている】
修復の方針は、切削前にすでに始まっています。
咬頭の残存量、隣接面の有無、器具操作のしやすさなど、多くの要素を見越して計画を立てるべき——でも、実際に削ってみると想定と違っていて、迷うことが多いのがリアルです。
たとえば、思ったよりもカリエスが深く咬頭を残せなかったり、歯質が脆くなっていたり…。
臨床では「教科書通りにいかない」ことが多々あるからこそ、自分なりの“修復基準”を持っておくことが非常に大切です。
【僕の「修復基準」を紹介します】
● 大臼歯
咬合面のみ or 根面カリエス → CR
隣接窩洞 → インレー以上(器具操作性が難しいため)
咬頭が2mm以上残存 → インレー
それ以下 → アンレー
根管治療あり → クラウン
再治療では、インレー or クラウン(やり直しを避けるため)
● 小臼歯
イニシャル治療
→ 咬頭2mm以上 → CR
→ 咬頭2mm未満 or 根管治療 → クラウン
→ アンレーは基本使わない
再治療(隣接面窩洞を含まない場合)
→ CR
再治療(隣接面窩洞あり)
→ 咬頭2mm以上 → インレー
→ 咬頭2mm未満 → クラウン
● 前歯
イニシャル治療 → 基本CR
根管治療後 → クラウン(変色や破折リスクのため)
再治療:複数面にわたるCRや脆弱な歯質の場合 → クラウン
ラミネートベニアは審美目的のみ
※オクルーザルベニアは接着信頼性の面で行わない
【 治療計画は「想定外」にも備えて】
こうした基準があっても「実際に削ってみたら想定よりも大きかった」というのは、臨床では日常茶飯事。
そんなとき、無理にCRやインレーで済ませようとすれば再治療につながるリスクもあります。
逆に、突然「クラウンに変更です」と伝えると、患者さんに不信感を与えるかもしれません。
だからこそ、治療前に“虫歯が大きい可能性”についてしっかり説明しておくことが非常に大切です。
たとえば、こう伝えるとよいでしょう:
「見た感じは小さそうですが、削ってみると中で広がっている可能性もあります。
その場合は歯の強度を考えて、クラウンやアンレーに変更することもあります」
そう伝えておくことで、いざ治療計画を変更しても「先生の言うとおりだった」と患者さんも納得できます。
もし想定よりも小さければ「良かった!」という安心感にもつながります。
【判断力は、フィードバックと経験で育てる】
もちろん、これが“正解”ではありません。
大事なのは、「なぜその修復を選択したのか」を自分の言葉で説明できること。
それが患者さんの理解を得るポイントにもなり、再治療の回避にもつながります。
判断力を高めるには:
- 自分の治療結果を経過観察する
- 他の先生の症例と比較・検討する
- 自分の失敗と成功を振り返り、軸をアップデートする
…といったフィードバックの積み重ねが重要です。
【まとめ】
- 削ったその先で迷わないために、自分なりの修復基準を持とう
- 計画変更が起きうることを先に伝えることで、患者との信頼関係が築ける
- 治療のゴールは「終わること」ではなく、「再治療にならないこと」
- 自分の今の実力で、患者にとって最善の治療を選ぶ姿勢が成長につながる
次回は患者さん向けの歯科情報を発信する予定です。みなさん正しいセルフケアの方法ご存じですか?次回もお楽しみに!
インスタもやっているのでぜひフォローお願いします!

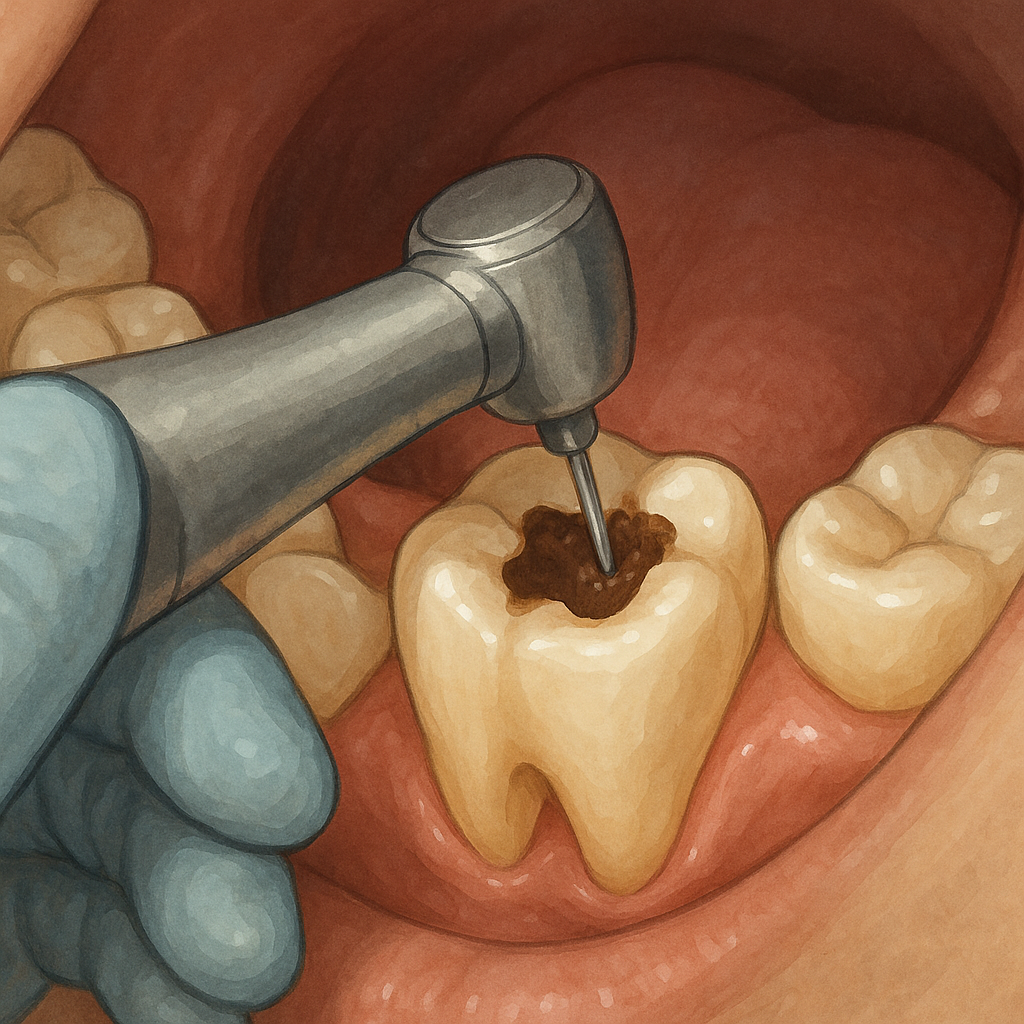


コメント