私たち若手の歯科医師が担当する新患さんは、定期検診希望だったり、歯石取り希望だったり、1本痛いという軽い症状で来院されることが多いと思います。重症例(崩壊症例や欠損歯が複数あるような難しいケース)が振り分けられることは少ないので、長期間の治療に繋がらないケースもよくあるのではないでしょうか。
ただし、実際には口腔内が理想的な患者さんなどほとんどいません。治療が続かないのは、自分の診断力や患者さんへの説明力がまだ未熟だからだと感じるようになりました。
上の先生が診れば、同じ患者さんでも治療が増えるのはよくある話です。
患者さんの主訴に応えることはもちろん大切ですが、術者の目から見て「理想的な口腔内」に近づけるために必要な治療をきちんとピックアップし、患者さんに説明する力が必要だと思います。例えば:
🦷 歯周病治療
検診希望の患者さんは、ポケットが4mm未満で一見正常なことが多いかもしれません。でも、BOP(出血)が理想的でない場合は、歯肉に炎症が起きていて、少し油断するとアタッチメントロスが進行するリスクがあります。他院では「歯石取って終わり、次回検診で」と済ませてしまう場合も多いと思います。
しかし、ここでBOPやポケットの話をしっかり伝えないことで、歯周病が検診を受けているのに進行してしまうケースがあります。
「ここが踏ん張りどころです。あなたの大事な歯を守るために、今しっかり歯周組織の健康を保ちましょう」と伝えるだけでも、患者さんの捉え方は大きく変わると感じます。
もちろん、ポケットが4mm以上の方には、検診だけでは済ませず再評価し、必要に応じてSRP(スケーリング・ルートプレーニング)などの加療を行う必要があります。
🦷 根尖病変
症状がなくても、根尖部に透過像(病変)が認められる場合は、「今後痛みが出るかもしれない」と説明しておくことが大切です。そうしておくと、いざ痛みが出たときに患者さんが「あの先生が言ってたやつかもしれない」と思い出して、治療を希望して来てくれる可能性が高まります。
🦷 不良補綴
マージン部に段差がある補綴物や、二次カリエスになりそうなリスクがある場合も説明しておくべきです。すぐ治療を開始する希望がなくても、「定期的にチェックして悪化しそうなら早めに処置が必要になりますね」と伝えることで、患者さんも安心して通ってくれるようになります。
🦷 咬合
理想的な咬合(犬歯誘導など)がある患者さんは稀です。前歯の機能が不十分で、臼歯に過剰な負担がかかっている場合、今後歯が壊れるリスクがあることも伝えておくと良いと思います。
また、食いしばりや歯ぎしりなどの力の問題についても、質問して話題にするだけで、患者さんが「自分の歯を守るためにできることは何か」と考えるようになります。その指針を示した歯科医師に対して「この先生に診てもらいたい」と感じてもらえるはずです。
若手の私たちは、患者さんの主訴への対応に加え、こうした「理想的な口腔内を目指すための説明力」を磨くことがとても大切だと思います。
私も半人前の歯科医師ですが、一歩ずつ診断力や説明力を磨き、患者さんの健康を長期的に支えられる歯科医師になりたいと感じています。
🌱 まとめ
主訴の解決はもちろん大切ですが、それだけでは患者さんの口腔内は守れません。
診断力と説明力を磨き、1口腔単位で将来を見据えた治療計画を立てることが、信頼される歯科医師への第一歩です。
若手のうちからこういった視点を持ち、一緒に成長していきましょう!
インスタもやっているのでぜひフォローお願いします!

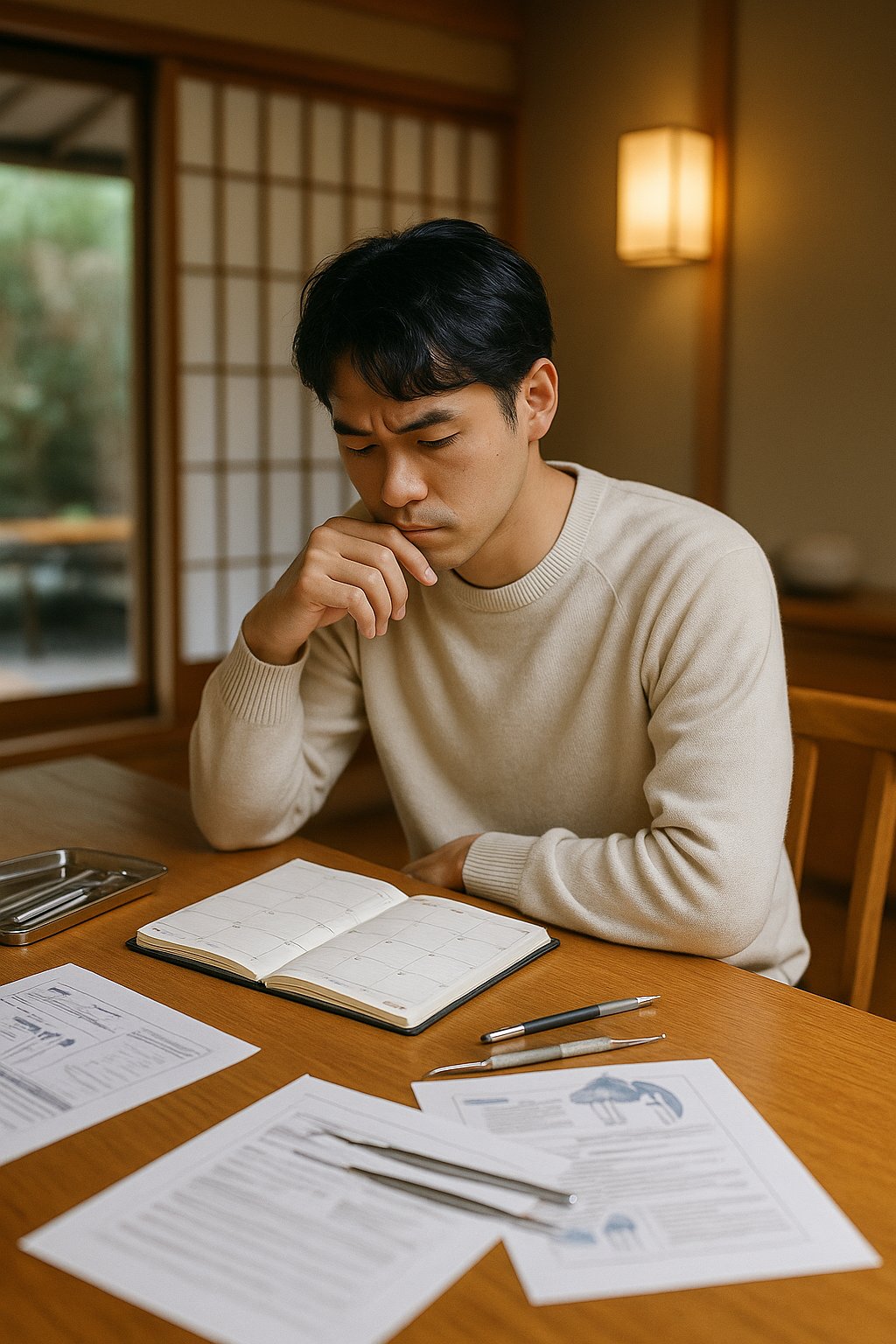

コメント